お役立ちコラム
ハラスメント対策について
ハラスメント対策はお済みですか?
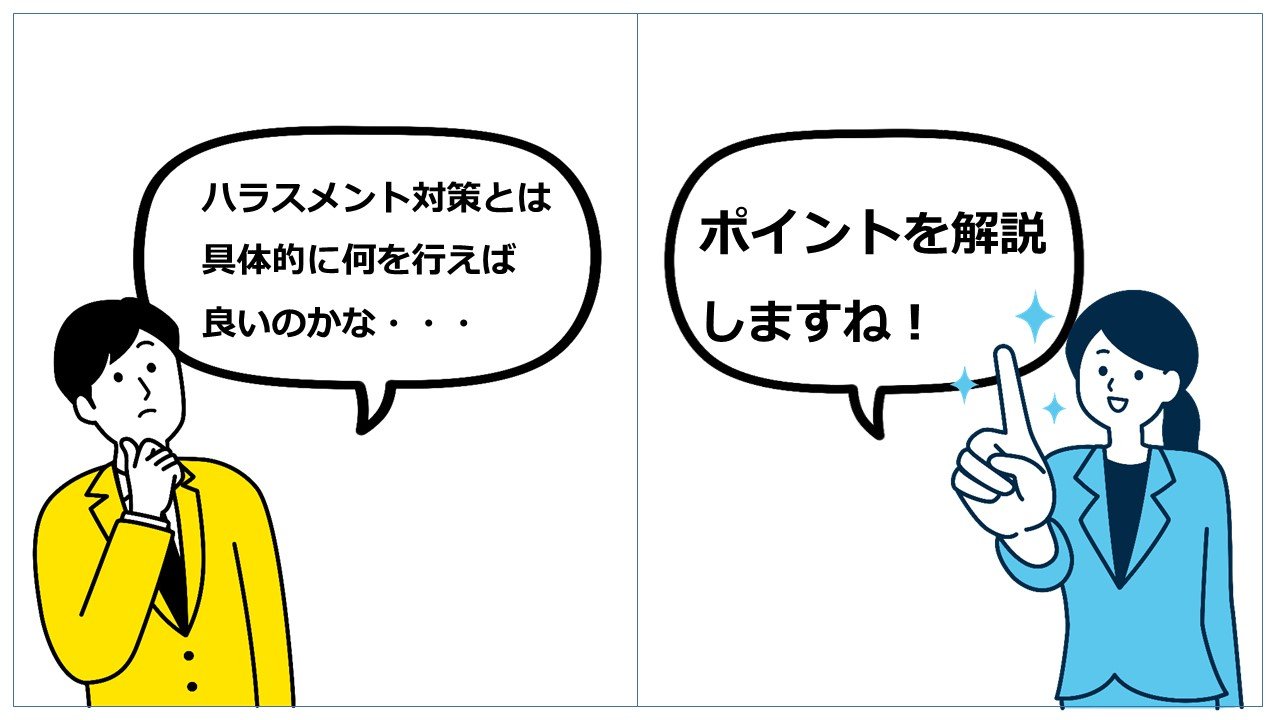
ハラスメント対策が事業主の責務とされており、法令上の対応が求められているところです。
具体的にどの様な対策が求められているか、ポイントを解説します!
目次
![]() 1.ハラスメント対策がなぜ重要なのか?
1.ハラスメント対策がなぜ重要なのか?
![]() 2.法的位置づけ
2.法的位置づけ
![]() 3.企業がとるべき対応
3.企業がとるべき対応
![]() 4.継続した取組
4.継続した取組
1.ハラスメント対策がなぜ重要なのか?
職場でのハラスメントは、職場環境を悪化させ、従業員のモチベーションの低下を招き、従業員が能力を十分に発揮することの妨げになりますし、個人としての尊厳や人格を傷つける許されない非道な行為です。
また、会社にとっても、優秀な人材の流出や、社会的評価への影響、働く従業員の士気の低下と、様々な面で、企業経営に悪影響をもたらします。
それでは、実態はどうなのでしょうか。職場のパワーハラスメントについては、2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した方は31.4%でした。
また、厚生労働省が公表した「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」においては、民事上の個別労働紛争の相談件数は、86,034件(前年度比8.6%増)で10年連続最多と年々増加傾向にあります。
つまり、ハラスメント対策は、法律上の義務はもとより、健全な職場環境を守っていくためにも、必要な対策と言えます。
2.法的位置づけ
ハラスメント対策は、ハラスメントの種類ごとに根拠となる法律が異なります。
「パワハラ」...労働施策総合推進法で対策が義務付けられています。
<労働施策総合推進法(抄)>
(雇用管理上の措置等)
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
「セクハラ」...男女雇用機会均等法で対策が義務付けられています。
<男女雇用機会均等法(抄)>
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力
した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱い
をしてはならない。
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第1項の措置の実施に関し必要な協力を
求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
「マタハラ」...男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で対策が義務付けられています。
<男女雇用機会均等法(抄)>
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第11条の3 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
<育児・介護休業法(抄)>
(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
根拠となる法律は異なりますが、対策の内容はほぼ同様とされております。
3.企業がとるべき対応
具体的に行うべき対策は以下(1)~(4)となります。
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※このほか、マタハラについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
(1)~(4)の各内容に関する概要は以下の通りです。
(1)周知・啓発
指針では、就業規則等にハラスメント禁止規定とハラスメントを行った者に対する懲戒規定を入れること、社内報・パンフレット・社内ホームページ当の広報・啓発のための資料にハラスメントの内容・発生原因や背景・ハラスメント禁止・懲戒の方針を記載し、配布すること、周知・啓発のための研修・講習を実施することが例示されています。
(2)相談体制の整備
指針では、相談担当者を決めること、相談対応の制度を設けること、外部機関に相談対応を委託することが例示されています。
(3)事後対応
指針では、「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」と「事実が確認できた場合、被害者に対する配慮の措置を適正に行う」と定められています。
(4)併せて講ずべき措置
プライバシー保護護のために必要な措置(プライバシー保護のために必要な事項を定めたマニュアルに基づき対応する等)を講じ、その旨を周知し、労働者が安心して相談できるようにする必要があります。
また、就業規則等に、労働者が職場におけるハラスメントの相談等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発することが求められます。
4.継続した取組
冒頭に記載した通り、法令上義務化されている取組である為、必ず実施しなければいけませんが、単に実施すれば良いということでは無く、なぜこの様な取組が必要なのかという目的を理解した上で、自社の状況に合っている取組となっているか、という視点も重要かと考えます。
ハラスメントは決して許されない行為であることの従業員教育、社内でハラスメント事案を目撃した時に相談窓口に通報できる仕組みの構築、ハラスメント事案が起こる社内では、当事者以外にも関係者が複数存在することが多いと思われます。
事件が大きくなる前に、早期発見できる仕組みの構築が求められます。
CSアカウンティングでは、規程作成や、研修動画・資料作成のサービスをご提供しております。
また貴社の現状をヒアリングし、貴社の状況に合うハラスメント対策のご提案も行わせて頂いております。
ご相談等ございましたらまずはお気軽にご相談頂ければと思います。
参考:厚生労働省HP
CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。
また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。
ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511
(執筆者:緒方)
関連コラム
- 令和7年度地域別最低賃金額改定について
- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
- 「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」が公表されました!
- 令和7年4月1日より、「介護離職防止のための雇用環境整備」や「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」が義務化されましたが、対応は進められているでしょうか。この度、厚生労働省から「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツ…
- 採用面接などで具体的に気をつけることは?
- 採用選考は企業と応募者の最初の接点です。企業の信頼性を高め、トラブルを防ぐためにも、基本的な考え方や注意点を押さえておきましょう。1.採用選考の基本的な考え方について採用選考は、「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人…
- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?
- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…
- 職場における熱中症対策が強化されます!
- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
