お役立ちコラム
償却資産税の期限はあっという間
はじめに
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、償却資産税についてです。
償却資産税は償却資産に係る固定資産税の通称であり、償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいい、例えば会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
1月1日現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに資産が所在する市区町村へ申告する必要があります。
申告期限が近づいてきましたので償却資産税の内容について確認をしていきましょう。
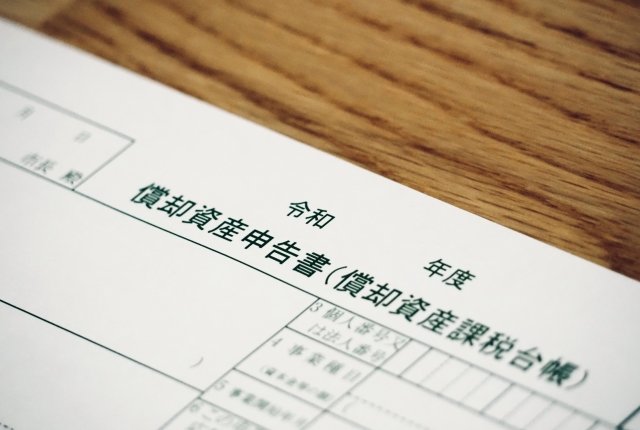
償却資産税について
1.申告対象資産
1月1日現在において、事業用に供することが出来る資産が申告の対象となる資産です。
なお下記のような資産も申告が必要となるので注意が必要です。
➀償却済資産(耐用年数が経過した資産)
②建設仮勘定で経理されている資産(完成して事業の用に供している部分)
➂遊休又は未稼働の資産
④改良費
⑤福利厚生の用に供するもの
⑥使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であって個別に減価償却しているもの
どれも申告を忘れてしまいそうな内容になっています。
償却済資産については一見税金はかからないようにも思われますが、税額算定の計算基礎となる課税標準の算定において、評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となるとされており、仮に簿価が0円であったとしても取得価額の5%をもとに税額が計算されてしまいます。
その為12月までには固定資産の実査を行い、廃棄等されている固定資産があれば除却処理をしておくようにしましょう。
2.申告の対象とならない資産
逆に次のような資産は償却資産の対象とならず申告は不要になります。
➀自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの
②無形固定資産(ソフトウエア、特許権等)
➂繰延資産(創立費、開業費、開発費等)
④平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産について
a.耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計以上固定資産として計上しないもの
b.取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
⑤平成20年4月1日以降に締結されたリース契約の内、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
3.償却資産税の課税方法
租税の課税方法には申告納税方式と賦課課税方式が存在し、償却資産税は償却資産について課される固定資産税という事もあり固定資産税の課税方式である賦課課税方式が採用されています。
賦課課税方式は国や地方公共団体が税額を計算し、納税者が通知された税額を納める方式ですが、土地や建物の場合は登記によってある程度市区町村が実態を把握できる一方で償却資産については困難です。
その為償却資産については所有者が1月1日現在所有する資産の種類や数量、取得時期や取得価額、耐用年数等を申告しその申告に基づいて市区町村が税額を計算することとなります。
少額の減価償却資産の取扱いについて
次に法人税法上の少額減価償却資産、一括償却資産、そして租税特別措置法の規定による中小企業者等の少額減価償却資産と償却資産税の関係についてまとめていきます。
1.少額減価償却資産
使用可能期間が1年未満の減価償却資産又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で、その取得価額相当額について法人税法施行令第133条の規定により損金の額に算入されたものについては償却資産に該当せず償却資産税は課されません。
ただし個別に資産計上した場合には償却資産として償却資産税が課税されるので注意が必要です。
2.一括償却資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産で、事業の用に供した事業年度において法人税法施行令133条の2に規定する一括償却資産として計上したものについては、償却資産に該当せず償却資産税は課税されません。
ただし少額減価償却資産と同様に個別に資産計上した場合には償却資産として償却資産税が課税されます。
3.中小企業者等の少額減価償却資産
租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定により、取得価額が30万円未満の減価償却資産でその事業の用に供した事業年度において損金の額に算入されたものについては償却資産税の対象となり、償却資産税が課税されます。
おわりに
今回は償却資産税の対象となる資産を中心に、償却資産税についてまとめさせていただきました。
日々適切に固定資産管理ソフトへ入力を行っていれば、年明けの忙しい時期も申告まで乗り切れるかと思いますが、対象となる資産をしっかりと把握できていなかったり、固定資産の実査を行っていなかったりするとばたばたして申告がぎりぎりになってしまうかもしれません。
そうならない為に償却資産税の内容を把握し、事前準備を徹底頂けますと幸いです。
この度は経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。
次回の経理・会計・税務コラムでまたお会いしましょう。
執筆者:笠井
関連コラム
- 法人税に関する改正措置について
- はじめに 今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、法人税の改正措置についてです。1.法人税に関する改正措置とは「令和7年度税制改正大綱」で法人税に係る措置として、中小法人の軽減税率の見直し及び防衛特別…
- 交際費と福利厚生費の違い
- はじめに交際費、福利厚生費どちらに該当するのかが争われた事例は数多くあります。そこで今回はどちらに該当するのかの判断基準を解説していきます。Ⅰ.交際費課税制度(1)制度の趣旨と改正の変遷交際費は昭和29年3月、租税特別措置法として成立しまし…
- 外国子会社合算税制(CFC税制)-令和6年度税制改正大綱-
- はじめにみずほ銀行がCFC税制の適用を巡り課税処分を争った事案が、昨年秋、最高裁にて結審しました。注目を集めたCFC税制について、令和6年度改正ポイントを解説します。1.CFC税制とは?CFC税制は、諸外国の例に倣い昭和53年日本にも導入さ…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
