お役立ちコラム
性同一性障害の方の社会保険手続きについて
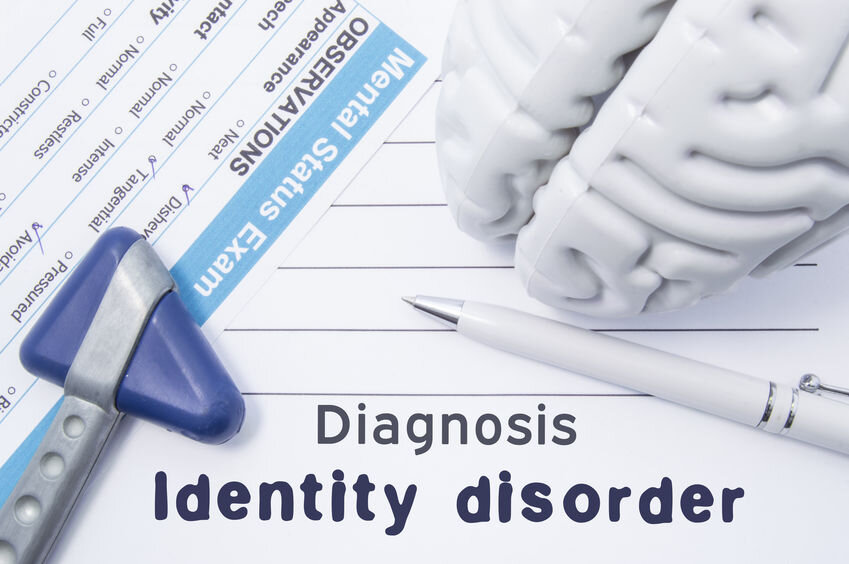
「性同一性障害」、昨今巷で耳にすることの多いキーワードですがご存知でしょうか?
性同一性障害(GID:Gender Identity Disorder)とは、自分の産まれ持った身体の性と、心の性(自分自身が自分の性をどう感じているか)が一致しない状態のことを指します。
1953年にアメリカの内科医によって報告された性同一性障害の概念は、その後世界中で認知されるようになりました。日本においても、対象の方が守られるよう、国を挙げて法整備がだいぶ整えられてきた印象ですが、
企業として健康保険証の取り扱いや労務管理上、どういった点に留意する必要があるか、今回はお話したいと思います。
(1)健康保険証の取り扱い
まず、社会保険の手続きについて、とりわけ、ご自身が常にお持ちになり、病院等に提示することが多い健康保険証の“性別”の記載についてですが、こちらは、実際に従業員の方からお問い合わせを受けたことのある人事担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
戸籍上の性別がそのまま記載されることに対し、抵抗を持たれる方は当然いらっしゃいます。
2013年、厚生労働省はある通達を出しました。それは「やむを得ない理由があると保険者が判断した場合に、保険証の表面ではなく裏面に戸籍上の性別を記載できるようにする」というものです。
「やむを得ない理由」とは、被保険者やその被扶養者が性同一性障害者であって、保険証の表面に戸籍上の性別が記載されることに対して嫌悪している場合等を指します。
保険者がこうした理由の有無を判断するのは難しそうですが、本人からの申出に加えて、性同一性障害の治療のために精神科等へ通院していることが診療報酬明細書等により確認できれば「理由あり」と判断して良いという一つの基準があります。
しかしながら、保険証の性別表記に嫌悪していることがわかれば、必ずしも精神科等に通院している必要はなく、医師の診断書も必ずしも求められてはいません。
もし、「やむを得ない理由」の有無が判別できない場合は、保険者の判断で診断書の提示を求めることも許されています。
また、裏面に戸籍上の性別が書いてあるなら表面は本人の望む性別を記載していいのではないかと思われますが、それは認められていません。
仮に、表面に戸籍上の性別とは異なる性別を記載した場合、保健医療機関等が裏面の確認をしなければ、裏面の戸籍上の性別を把握することができないからです。あくまで表面の性別欄は、裏面参照か戸籍上の性別の記載が必要となります。
ちなみに、表面の性別欄に「裏面参照」の記載をなくし、空欄とすることも、外見での性別判断につながるおそれがあるため認められません。
なお、高齢受給者証や限度額適用認定証、介護保険の被保険者証等についても、本人からの申出があれば、同じ対応が受けられます。
次は、氏名表記についてです。2017年、厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う“通称名”を、健康保険証の氏名欄に記載することを認めると都道府県や医療保険者に通知をしています。
今も国民健康保険の保険証では使えるとしているが、医療機関の窓口で見た目の性と異なる名前で呼ばれる精神的苦痛などに配慮し、すべての健康保険証で記載できることになりました。
通知は8月31日付で、本人や家族から希望があり、保険者が認めた場合、裏面に戸籍上の氏名を併記し、表面に通称名を記載できるといったものです。
このように、健康保険証の表記一つにおいても、適切に対応できるよう、こういった知識を企業の人事担当は持っておくと良いでしょう。
なお、年金手帳の表記については、本人からの訂正申告がある場合、訂正可能です。雇用保険被保険者証も訂正可能です。必要あれば、最寄りの年金事務所、ハローワークに詳細をお問い合わせしてみて下さい。
(2)労務管理上の注意点について
例えば対象となる従業員の方がトイレの使用について、自身は戸籍上男性であるけれど、性同一性障害であるため、できれば女性トイレを使用したいと相談してきたらどのように対応したら良いでしょう?
各個人の性格や置かれた状況等、それぞれの事象において何が正しいのか、何が最適な回答なのか明瞭な正解はありませんが、対象の従業員の方が言われなき差別を受けないように、けれど、無理なく過ごすための環境を構築するためにはどうしたらいいか、という視点で考えると、答えは見えてくるかもしれません。他の従業員の方の理解も必要あればどのように得るか等、課題は多くあると思いますが、企業として必要な対応でもあるため、考えていく必要があるでしょう。
また、LGBTの問題は、いつ直面するか分からないですから、予め想定して準備や心構えを行っておく事も必要だと言えます。慢性的な人手不足時代に、多様性に対応出来る企業は、他社と差別化を図れることでしょう。多様性の一つとしてLGBT対策も怠らない様にしていく事が求められます。
また、多様性に寛大な企業は、様々な方が働きやすい企業とも言えますので、人材の定着率増加への良い効果も期待出来ます。
関連コラム
- 【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
- 令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…
- 被用者保険の適用拡大
- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…
- 2028年4月施行予定 遺族厚生年金の見直しについて
- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しています。この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機…
- オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?
- オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…
- 令和7年4月から現物給与の価額が改正されます
- 今回は社会保険における現物給与についてお伝えいたします。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
