お役立ちコラム
電子帳簿保存法とは?令和5年度税制改正のポイント解説
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、今まで原則として紙での保存が義務付けられていた帳簿書類について、所定の要件を満たした場合、紙ではなく電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすることを定めた法律です。また、電子データとして授受した情報の保存義務等も定められています。
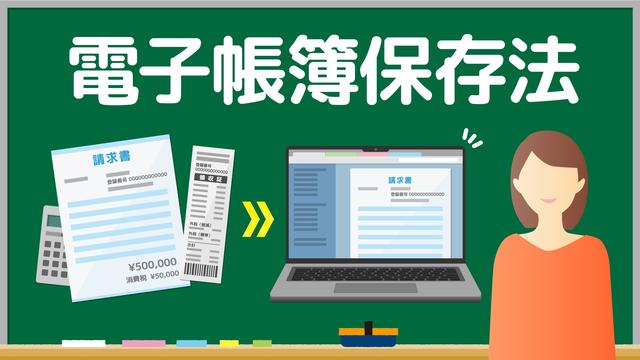
電磁的記録による保存用件
自己が会計ソフトやシステムで一貫的に作成した、帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)や書類(請求書など)について、電子帳簿保存法で定められた一定の要件を満たせば、紙媒体での出力は不要となり、電子データのまま保存することができます。
具体的に、電子帳簿保存の対象となる書類には、下記のもの該当します。
- コンピュータを使用して作成する帳簿 (例)仕訳帳、総勘定元帳
- コンピュータを使用して作成する決算関係書類(例)貸借対照表、損益計算書
- コンピュータを使用して作成し、取引相手に交付する書類の写し(例)請求書、領収書
※正規の簿記の原則に伴い、整然と且つ明瞭に記録されていることが必須です。
※一部の帳簿のみを、電子データによる保存とすることも可能です。
上記の書類は、「自己が一貫して」作成することが前提となっています。「自己が一貫して」作成するということは、自己が最初の記録段階から、一貫して電子計算機を使用して作成することとされています。従って、電子計算機を使用して作成した書類を出力し、それに手書きで情報を加筆したものは、電磁的記録による保存用件を満たさなくなるので、書面による保存が必要となります。
優良な電子帳簿について
優良な電子帳簿とは、一般の帳簿の保存用件に加えて、下記のような用件を満たす電子帳簿のこととなります。
| 電子帳簿の保存用件 |
| 記録事項の訂正・削除を行った場合、これらの事実・内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること |
| 通常の業務期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること |
| 電子化した帳簿記録と、その帳簿に関連する他の帳簿記録との間で相互に関連性を確認できること |
| システム関係書類を備え付けること (例)システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなど |
| 保存場所に電子計算機・ディスプレイ・プリンタ等の設備及び操作マニュアルを装備し、記録事項を明瞭な状態で速やかに出力できること |
| 検索用件として、取引年月日・取引金額・取引先を検索できる |
| 検索用件として、日付または金額の範囲指定によって検索ができる |
| 検索用件として、2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できる |
優良な電子帳簿を使用する場合、下記のようなメリットを受けられます。
・帳簿の記録に誤りがあり、過少申告加算税を課された場合に、5%の軽減措置を受けることができる
・要件を満たした仕訳帳及び総勘定元帳の保存を行う場合、所得税の青色申告特別控除(65万円)を受けることができる
令和5年度 電子帳簿保存法の税制改正について
令和5年より、電子帳簿保存法について、下記の税制改正があります。
- 優良な電子帳簿の範囲の見直し
- スキャナ保存制度の見直し
- 電子取引の取引情報にかかる電磁的記録の保存要件の見直し
- システム対応が間に合わなかった事業者等への対応
1.優良な電子帳簿の範囲の見直し
仕訳帳・総勘定元帳以外の優良な電子帳簿が下記の事項を記載する帳簿となり、範囲が明確化されます。
【改正前】仕訳帳・総勘定元帳以外の帳簿は、保存しなければならない全ての帳簿である
【改正後】仕訳帳・総勘定元帳以外の帳簿は、以下の事項を記載した帳簿である
- 売上やその他収入に関する事項 (例)売上帳
- 仕入やその他経費、または費用に関する事項(賃金、給料手当、法定福利費、厚生費を除く) (例)仕入帳、経費帳
- 売掛金やその他債権に関する事項 (例)売掛帳
- 買掛金やその他債務に関する事項 (例)買掛帳
- 手形上の債権債務や有価証券に関する事項 (例)受取手形記入帳、仕入手形記入帳
- 減価償却資産、繰延資産にかかる事項 (例)固定資産台帳、繰延資産台帳
適用時期は、令和6年1月1日以後に、法定申告期限等が到来する国税が摘要となります。
2.スキャナ保存制度の見直し
国税関係書類のスキャナ保存制度について、要件の廃止および対象となる書類が限定されます。
- スキャナで読み取った際の解析度、階調・大きさに関する情報の保存用件が廃止になります。
- 記録事項の入力者に関する情報の確認要件が廃止になります。
- 国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項について、相互に関連性を確認する書類が、「重要書類、資金や物の流れに直結・連動しない一般書類」から「契約書・領収書等の重要書類のみ」に変更されます。
適用時期は、令和6年1月1日以後に保存される国税関連書類となります。
3.電子取引の取引情報にかかる電磁的記録の保存要件の見直し
- 検索要件の全てが不要となる売上高の条件が、売上高1,000万円以下の事業者から、5,000万円以下の事業者に引き上げられます。
- 電磁的記録の出力書面を日付および取引先ごとに整理して保存をしている場合、検索要件の全てが不要となります
- 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件が廃止されます。
適用時期は、令和6年1月1日より適用となります。
4.システム対応が間に合わなかった事業者等への対応
保存用件に沿って電磁的記録を保存できなかったことについて、相当の理由がある事業者については、検索機能の確保の要件等を不要にしてデータの保存を可能とする、新たな猶予措置が整備されます。また、現行の経過措置は適用期限(令和5年12月31日)をもって廃止となります。
【改正前】
・摘要要件は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合であり、出力書面の提示・提出の要求に応じることができる場合である。
・実務対応は、事実上、出力書面による保存が可能となる。
・保存期間は、出力書面について、事実上、税務調査機関の保存が必要である。
【改正後】
・摘要要件は、税務署長が相当の理由があると認める場合であり、出力書面の提示・提出、及びデータのダウンロードの要求に応じることができる場合である。
・実務対応は、データの保存が必要である。
・保存期間は、データ及び出力書面について、事実上、税務調査機関の保存が必要である。
適用期間は、令和6年1月1日より適用となります。
おわりに
電子帳簿保存法への対応は、それぞれの企業でケースバイケースのため、画一的な対応方法は無く、自社に合った方法を模索しているうちに時間が過ぎていってしまいます。
組織全体の抜本的な見直しや、システムの大掛かりな改修が難しい場合は、まずは「どこに無駄があるか」を特定し、その無駄の削減に取り組みつつ電子帳簿保存法にも対応していくということが大切です。
弊社では、会計業務のアウトソーシングを行っております。例えば、立替経費の精算業務などをアウトソーシングすることで、業務時間の削減や電子帳簿保存法への対応時間が確保できます。また、専門家のノウハウを享受しながら業務の効率化と電子帳簿保存法に適応したシステムの導入を同時に進めていくことも可能です。
業務のアウトソーシングや電子帳簿保存法について詳しく知りたい場合は、CSアカウンティング株式会社まで、お気軽にお問合せください。
関連コラム
- 損金算入となる飲食費の基準変更について
- はじめに 2023年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が公表され、税務上損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費にかかる金額基準についての見直しがありました。公表されてから半年以上経過しているため、既にご存知の方も多いと思い…
- 納付書の事前送付の取りやめについて
- はじめに 国税庁のホームページに「納付書の事前送付に関するお知らせ」というものが掲載されているのはご存じでしょうか。 今までは申告や納付期限が近付くと所轄の税務署から納付書が送付されておりましたが、キャッシュレス納付の利用拡大、社会全体の効…
- リース会計処理の改正について
- はじめに2023年5月2日付で、企業会計基準委員会日付で、企業会計基準委員会(ASBL)より「リースに関する会計基準(案)」および「リースに関する会計基準の適用指針(案)」が公表されたことをご存知でしょうか?今回のリースに関する会計基準の改…
- インボイス制度における2割特例とは
- はじめについに令和5年10月1日よりインボイス制度の適用が開始されました。インボイス制度に対応するために、免税事業者から課税事業者へ変更することにした事業者の消費税計算について、「2割特例」が新設されたことはご存知でしょうか。今回は、その「…
- 今更聞けない!?インボイス制度について
- インボイス制度とはインボイス制度とは、2023年10月より適用される制度であり、仕入税額控除の要件として適格請求書(インボイス)の保存が義務化されるという内容の制度です。そもそも適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して正確に摘要…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
